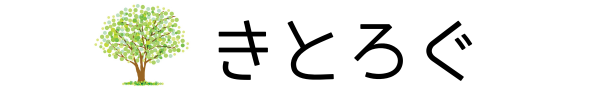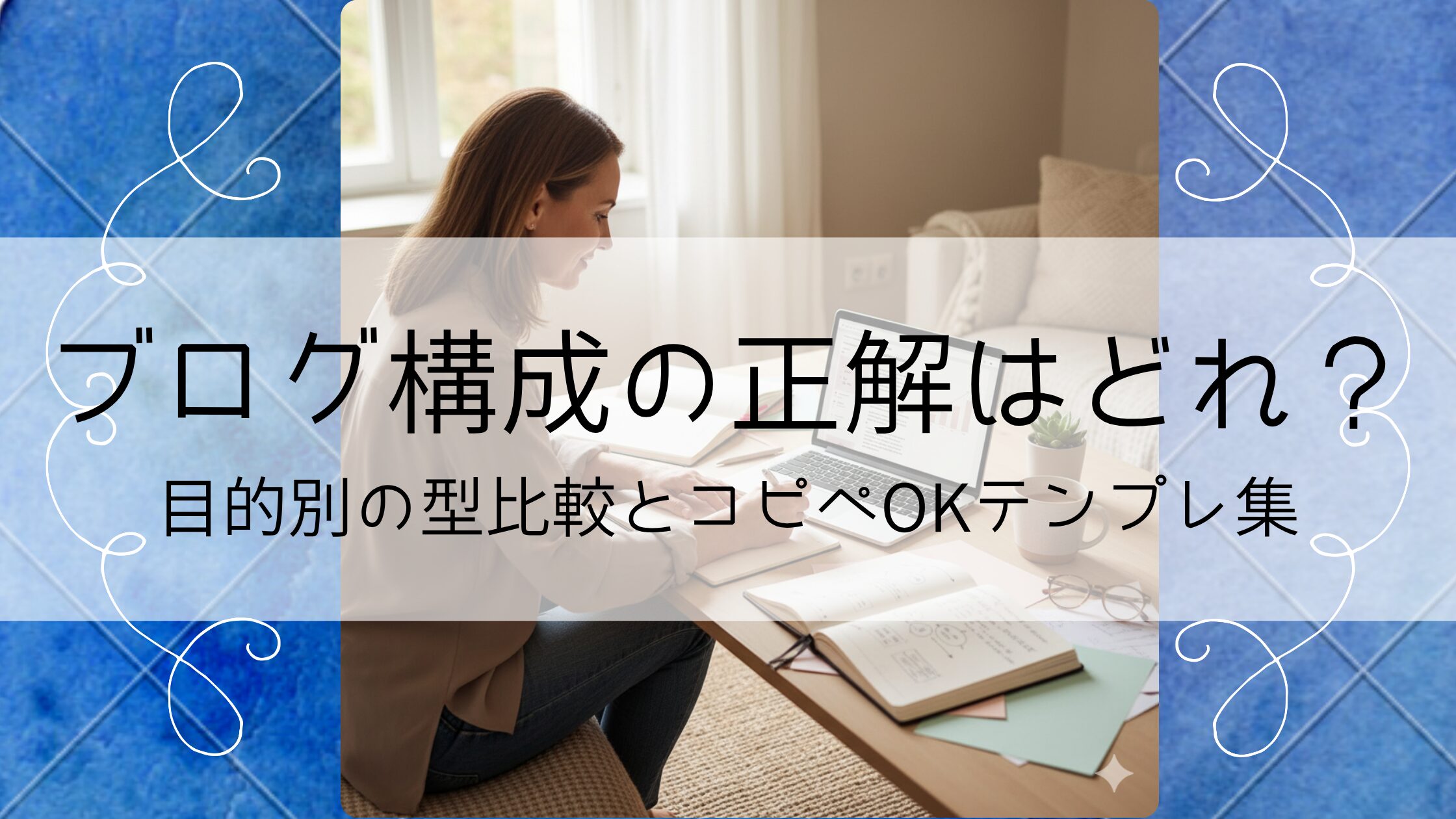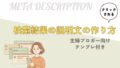ブログの構成って、結局どの型が正解なの?毎回迷っちゃう…
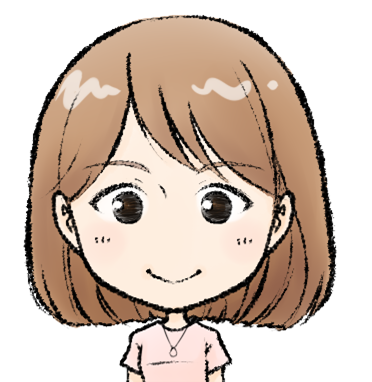
じつは「記事の目的」によって、使う型が変わるんだよ。
コツを覚えれば、型選びで迷わなくなるよ!
ブログを書いていて、
「リード文までは書けたけど、本文の流れが決まらない」
「PREP?HowTo?どれを使えばいいの?」
そんな「構成迷子」になったことはありませんか?
この記事では、ブログ記事の構成パターンを5つに整理し、
それぞれの「向いているテーマ」「見出しテンプレ」「使い分けのコツ」をまとめました。
どの型を選べばいいのか、目的別にすぐ判断できる比較表とコピペOKテンプレもご紹介。
「型」を知ることで、構成を考える時間がぐっと短くなり、
最後までスッキリ読まれる記事が書けるようになりますよ。
記事構成パターンは何種類ある?
ブログ記事の構成には、いくつかの「型」があります。
どんな記事も、実はこの中のどれかに当てはまっているんです。
やみくもに書き始めるより、あらかじめ型を決めておくことで、
迷わずスムーズに書き進められるようになります。
初心者が覚えるべき5つの型
① PREP型(結論→理由→例→まとめ)
② HowTo 5ステップ型(手順解説に強い)
③ 問題→原因→対策型(悩み解決に最適)
④ レビュー型(比較・購入前の不安解消)
⑤ FAQ型(質問まとめ・内部リンク誘導
これらはすべて、目的の違いに合わせた「型」です。
たとえば「読者の悩みを解決したい」のか、「手順を伝えたい」のかで最適な構成は変わります。
※PREPの基本構成の詳しい解説は、こちらの記事をご覧ください。
どの型を選ぶ?目的別の使い分けフローチャート
読者の検索意図をチェックしよう
まず大切なのは「読者が何を求めて検索しているか」を考えることです。
検索意図を整理すると、自然と使うべき構成型が見えてきます。
- 今すぐ答えが知りたい → PREP型
- 手順をじっくり学びたい → HowTo 5ステップ型
- 悩みを根本から解決したい → 問題→原因→対策型
- 比較して選びたい → レビュー型
- 細かい疑問をまとめて知りたい → FAQ型
勝ちパターンの選定ロジック
型を決めるときは「時間・素材・ゴール」の3つを意識しましょう。
- 時間:短時間で伝えたいならPREP型
- 素材:画像や手順が多いならHowTo型
- ゴール:購入・申込みにつなげたいならレビュー型
自分が書く目的を明確にしておくと、「どの型で書けばいいか」迷いが減ります。
用途別テンプレと見出し雛形
① PREP型
「どうやってまとめればいいのかな…」と悩んだときに便利なのが「PREP型」です。
結論から伝えることで、読む人がすぐ理解できる流れになります。
ここでは、その書き方と簡単な型の使い方を紹介しますね。
H2:結論:○○は△△です
H3:理由:なぜなら〜だから
H3:具体例:実際にやってみた結果
H3:まとめ:読者への提案「短くまとめたい」「結論をすぐ伝えたい」ときにおすすめの構成です。
※PREPの基本定義は ブログ記事の基本の流れとPREPの基礎 をどうぞ。
② HowTo 5ステップ型
やり方や手順をわかりやすく伝えたいときにぴったりなのが「HowTo 5ステップ型」です。
ひとつずつ順番に進めていく構成なので、読者も安心して読み進められます。
家事・節約・レシピなどの実践系にも相性がいいですよ。
H2:手順の全体像
H3:STEP1 準備するもの
H3:STEP2 基本操作
H3:STEP3 注意点
H3:STEP4 応用テクニック
H3:STEP5 仕上げチェック
家事・節約・料理など、実践系の記事とも相性が良い型です。
HowTo型ブログ構成の作り方(画像配置・CTA位置も解説)
操作手順の書き方に迷ったら → WordPressで投稿してみよう(ブロック操作の基本)
③ 問題→原因→対策型
読者の悩みを丁寧に解決したいときは、「問題→原因→対策型」がおすすめです。
まず「なぜそうなるのか?」を説明してから対策を提案することで、
納得感のある記事になります。
共感を大切にしたいときにも使いやすい構成です。
H2:問題:○○に悩んでいませんか?
H3:原因:なぜ起こるのか
H3:対策:今すぐできる解決法
H3:再発防止:長く続けるコツ悩み系・失敗談・改善策など、「読者の不安に寄り添う記事」で使いやすい型です。
④ レビュー型
商品やサービスを紹介するときに役立つのが「レビュー型」です。
実際に使った感想や比較を交えながら、読者の不安をやさしく解消していく構成です。
「買ってよかった」「私にもできそう」と感じてもらえる流れを作りましょう。
H2:結論:おすすめできる人/できない人
H3:特徴と使ってみた感想
H3:メリット・デメリット
H3:他製品との比較表
H3:よくある質問Q&A
H3:購入・申込み方法
レビュー記事では、正直さと実体験の具体性が大切です。
「本音+データ」で書くと信頼性が高まります。
⑤ FAQ型
よくある質問をまとめたいときや、細かい疑問に答えたいときにぴったりなのが「FAQ型」です。
読者の「これも知りたかった!」を拾えるので、信頼感のある記事づくりに役立ちます。
内部リンクを張れば、他の記事への導線にもなりますよ。
H2:質問一覧(サジェストやコメントから収集)
H3:Q1:〜?
A:短く回答 → 詳しくは関連記事で詳しく解説しています
H3:Q2:〜?
A:同上
FAQ型は検索の取りこぼしを防ぎ、サイト全体のSEOを底上げしてくれます。
同じテーマを型違いで書く練習
見出し設計のコツも合わせて確認 → ブログ見出しの作り方完全ガイド
テーマ例:電気代の節約を5型に変換
たとえば「電気代の節約」という同じテーマでも、構成の型を変えるだけで
読者への伝わり方や記事の印象が大きく変わります。
ここでは、5つの構成パターンを使って実際に書き分ける例を見ていきましょう。
① PREP型(結論→理由→具体例→まとめ)
まずは「結論を先に伝える」王道のPREP型です。
記事の冒頭でズバッと答えを示すことで、読者の関心を一気に引き寄せられます。
- 結論:電気代を減らすなら「エアコン設定温度を1℃下げよう」
- 理由:冷房温度を1℃変えるだけで年間1,000円以上の節約になるため
- 具体例:我が家では設定温度を27℃→28℃にして月500円節約
- まとめ:無理なくできる小さな工夫から始めよう
短く説得力のある内容にしたいときに向いています。
② HowTo 5ステップ型(手順で導く構成)
やり方や手順をしっかり伝えたいならHowTo型がぴったり。
手順を「STEP1〜5」に分けて説明することで、読者が行動しやすくなります。
- STEP1:電気使用量をチェック
- STEP2:使っていない家電のコンセントを抜く
- STEP3:冷蔵庫の温度設定を「中」にする
- STEP4:エアコンのフィルターを掃除する
- STEP5:電気会社のプランを見直す
実践型・生活系のブログ記事と相性が良い構成です。
③ 問題→原因→対策型(悩み解決に強い構成)
読者の悩みを丁寧に整理して、解決へ導く型です。
「なぜ電気代が高いのか?」という問いを中心に据えて書くのがポイント。
- 問題:毎月の電気代が高くて家計が苦しい
- 原因:待機電力のムダ・冷房の使いすぎ・古い家電の低効率
- 対策:プラン見直し・節電タイマー活用・LED化など
- 再発防止:月1回の電気使用量チェックを習慣にする
共感を生みやすく、検索上位にも強い構成です。
④ レビュー型(比較・体験重視)
実際に使ってみた節電グッズを紹介するレビュー型です。
「どれを買おうか迷っている読者」に向けて書くと効果的です。
- 結論:「スマートプラグ」は消し忘れ防止に便利でおすすめ
- 特徴:スマホで家電の電源をオン・オフできる
- メリット:待機電力を自動カットできる
- デメリット:Wi-Fi環境がないと使えない
- 比較:他の節電グッズ(節電タップ・タイマー)との違い
- 購入方法:Amazon・楽天など主要通販で入手可能
レビュー記事は写真を添えると信頼度がぐっと上がります。
レビューの書き出しと比較表の作り方は → レビュー記事の書き方
⑤ FAQ型(質問に答える構成)
「よくある質問形式」でまとめると、初心者にも親切です。
検索の取りこぼしも拾えるので、サイト全体の回遊率アップにも役立ちます。
- Q1:電気代の節約って何から始めればいい?
→ A:まずは「待機電力のムダ」を減らすことから。 - Q2:節電グッズって本当に効果あるの?
→ A:正しく使えば年間で数千円の節約になるケースも。 - Q3:我が家でも簡単にできる方法は?
→ A:冷蔵庫や照明など「毎日使う家電」から見直すのがおすすめ。
FAQ型は情報を一覧にまとめたいときや、他の記事へ誘導したいときに便利です。
FAQから関連ページへつなぐ導線づくり → FAQ型テンプレの実例
このように、同じ「電気代の節約」というテーマでも、
構成の型を変えるだけで「印象」「読者層」「SEOキーワード」がすべて変わります。
型を使い分けることで、1つのテーマから複数の記事を生み出すこともできるんです。
同じテーマでも構成を変えると、ターゲット読者や流入キーワードが変わります。
見出しの並び替えとCTAの変え方
構成の型が違うと、読者が「行動したくなるタイミング」も変わります。
CTA(行動喚起)は、記事の内容や流れに合わせて置き場所を調整するのがコツです。
ここでは、型ごとのおすすめ配置と文例を紹介します。
① PREP型は「まとめ」の直後がベスト
PREP型は結論→理由→具体例→まとめの流れで、読者の理解がスッキリ完結します。
そのため、読後すぐに「次の行動」を提案するとスムーズに動いてもらえます。
- おすすめのCTA位置:まとめ文の直後
- 文例:「詳しい手順はこちらの記事で紹介しています」
- 効果:理解直後に次の記事へ自然に誘導できる
PREP型は短文でまとまる記事が多いため、CTAを長く書くよりも
1文+リンクボタンのシンプル構成が効果的です。
② HowTo型は「最後のステップ内」に配置
HowTo型は、読者が実際に手順を追いながら読み進める構成です。
STEP5(仕上げチェック)など「やり終えたタイミング」でCTAを入れると自然です。
- おすすめのCTA位置:STEP5や最後の手順ブロック内
- 文例:「この手順をもっと詳しく知りたい方は、こちらの講座もおすすめです」
- 効果:「できた!」という達成感と同時に次の行動へつなげられる
また、手順の途中(STEP2〜3)で補足記事へリンクを差し込むのも有効です。
読者が詰まりそうなポイントに内部リンクを置くと離脱防止にもなります。
③ 問題→原因→対策型は「対策」の直後に配置
悩み解決記事では、読者は「対策部分」で安心感を得たあとに行動しやすくなります。
そのタイミングでサービスや関連記事を紹介しましょう。
- おすすめのCTA位置:対策パートのすぐ下
- 文例:「この方法で解決できない場合はこちらの記事も参考にしてください」
- 効果:悩みが解消された直後のクリック率が高い
最後の「再発防止」パートでは、メルマガ登録やLINE案内など
「継続フォロー」のCTAを置くと相性が良いです。
④ レビュー型は「記事下」に配置
レビュー型は比較・体験・疑問解消を経て読者が「納得」したタイミングでCTAを入れます。
途中で売り込みを感じさせず、最後まで読んでから行動してもらうのが自然です。
- おすすめのCTA位置:「よくある質問」や「まとめ」の直後
- 文例:「この商品をお得に試したい方は、公式サイトをチェック」
- 効果:記事を読み終えた後の信頼感を活かせる
レビュー型では、本文内では売り込みをせず、最後で背中を押すのが成功パターンです。
⑤ FAQ型は「各回答の下」または「最後にまとめて」
FAQ型は質問と回答が並ぶ構成なので、CTAを各Q&Aの下に入れるか、記事の最後にまとめて置きます。
- おすすめのCTA位置:各回答下または最終Q&A後
- 文例:「この疑問について詳しく知りたい方は→関連記事へ」
- 効果:サイト内回遊が増え、SEOの評価も高まる
FAQ型は「関連情報をつなぐハブ記事」としても使えるため、
各回答に内部リンクを入れることで自然に回遊導線が作れます。
型ごとのCTA配置まとめ
| 型の種類 | おすすめ位置 | CTAの目的 |
|---|---|---|
| PREP型 | まとめの直後 | 次の記事へ誘導 |
| HowTo型 | 最後のステップ内 | 行動・サービス紹介 |
| 問題→原因→対策型 | 対策または再発防止の直後 | 追加情報・継続支援 |
| レビュー型 | 記事下 | 購入・申込み |
| FAQ型 | 各回答下または最後 | 関連記事誘導 |
型によって読者の「心理的ピーク」が変わるため、
その流れに合わせてCTAを配置することが、自然で押しつけがましくない導線づくりのポイントです。
型ごとのCTA文例テンプレート集
ここでは、記事の最後や途中に自然に入れられるCTA(行動喚起)文の例を紹介します。
「売り込み感がない」「読者が安心してクリックできる」やさしい表現にしています。
① PREP型:まとめ文のあとに入れるCTA
理解直後に「もう少し詳しく知りたい」と思う読者に向けて、軽い導線を設置します。
PREP型は1文+リンクボタンのようなシンプルな形が効果的です。
② HowTo型:STEP5(仕上げチェック)内に置くCTA
行動完了後に「次のステップ」を提案すると自然です。
HowTo記事では、成功体験とセットで提案すると押しつけがましく感じません。
③ 問題→原因→対策型:対策パートの直後に配置
解決の安心感が生まれたタイミングで「次の行動」を提案します。
再発防止の章で「無料チェックリスト配布」や「メルマガ案内」などを入れるのもおすすめです。
④ レビュー型:記事の最後に置くCTA
読者が「比較して納得した直後」に、購入・申込みにつなげるCTAを配置します。
💡 内部リンク型:
「他のおすすめ○○も気になる方はこちら → 比較記事を読む」
🛒 アフィリエイト型:
「今なら公式サイトで割引キャンペーン中!→ ○○公式サイトを見る」
レビュー記事では、本文中では売り込みを避けて、信頼関係ができた最後で案内するのが自然です。
⑤ FAQ型:各回答の下または記事末に配置
FAQ型では、回答後に「詳しくはこちら」と自然につなげるとクリック率が上がります。
最後の質問のあとに「この記事で解決できなかった方はこちらもどうぞ」など、まとめリンクを入れると親切です。
CTA文の作り方のコツ
- 「〜してください」ではなく、「〜してみませんか?」とやわらかく言う
- リンクテキストは「こちら」だけでなく、「○○を見る」「○○をチェック」など具体的に
- 吹き出しやボタンを使うとタップ率UP(Cocoonのボタンブロックが便利)
読者に安心感を持ってもらうには、
まず「情報提供 → 提案 → 行動」の順番を意識するのがポイントです。
この流れを守るだけで、クリック率が自然に上がります。
「型の選び間違い」を見抜く5つの質問
「なんとなくまとまらない…」と感じたら、構成型が合っていない可能性があります。
下の質問に答えることで、自分の記事にぴったりな型が見えてきます。
- この記事の目的は「説明」「比較」「解決」どれ?
→ 「説明」ならHowTo型、「比較」ならレビュー型、「解決」なら問題→原因→対策型。 - 読者が一番知りたいのは「結論」?「やり方」?
→ 「結論」ならPREP型、「やり方」ならHowTo型が向いています。 - 画像や手順は多い?それとも文字中心?
→ 画像・手順が多いならHowTo型、文字中心ならPREP型や問題→原因→対策型がおすすめ。 - 体験談を入れた方が伝わる?
→ はい→PREP型かレビュー型。
→ いいえ(淡々と説明したい)→HowTo型やFAQ型。 - 最終的に読者に何をしてほしい?
→ 行動してほしい(申込み・購入)→レビュー型。
→ 別記事へ誘導したい→PREP型・FAQ型。
→ 実際にやってほしい→HowTo型。
この5つに答えるだけで、今のテーマに合う「構成の型」が自然に見えてきます。
うまくハマらないときは、型を変えるだけで驚くほど書きやすくなることもありますよ。
次に読むおすすめ記事
ここまで読んで「自分に合う型が見えてきた!」という方は、
次のステップとして下の記事もチェックしてみてください。
どれも今回の内容とつながっていて、すぐ実践に役立ちます。
- ブログ記事の基本の流れとPREPの基礎 … 記事構成の基本とPREP法の使い方をやさしく解説。
- ブログ見出しの作り方完全ガイド|H2・H3の使い分けと構成テンプレ付き … 型に合わせた見出し設計の具体例を紹介。
- PREP法の使い方|主婦ブログでも伝わる「結論→理由→具体例→まとめ」の書き方 … PREPを実践で使いこなすコツとテンプレート。
- クリックされる検索の説明文の作り方|主婦ブロガー向けテンプレ付き … 検索で選ばれるタイトルとメタディスクリプションの書き方を解説。
記事の型を選べるようになると、書くスピードも迷いもぐっと減ります。
「どの型で書こう?」と悩んだときは、またこのページに戻ってきてくださいね。

型を意識したら、なんだか書くのが楽しくなってきたかも!
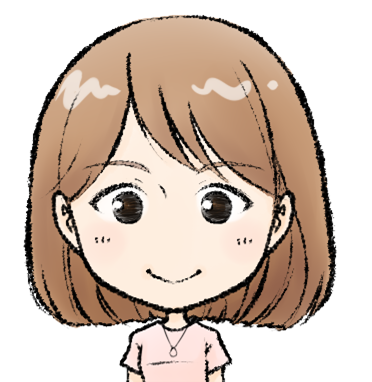
それが一番大事だよ。まずは一つの型から、自分らしく試してみよう!